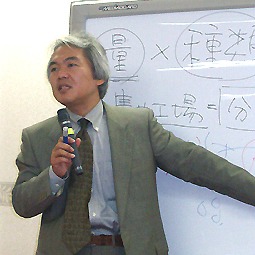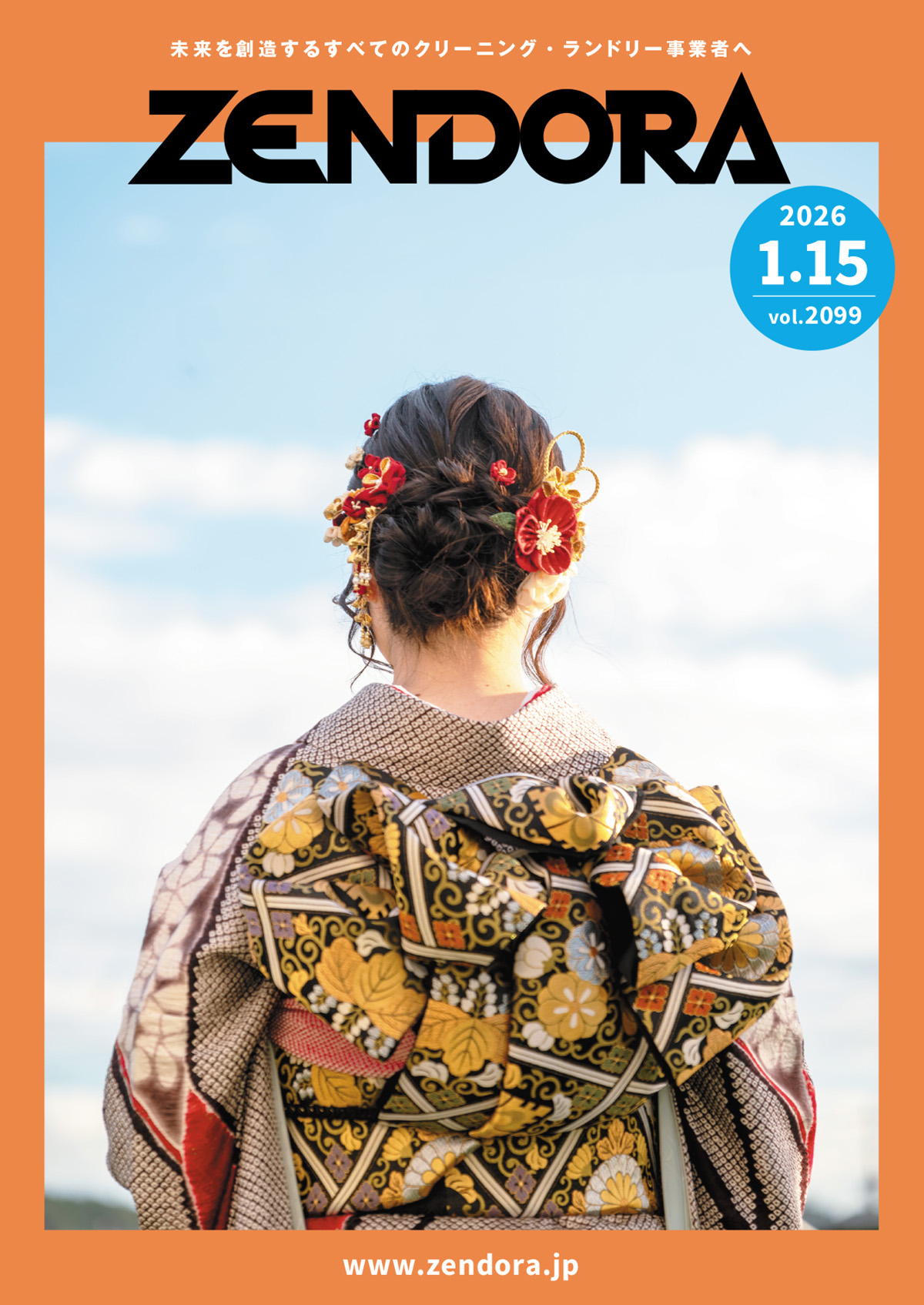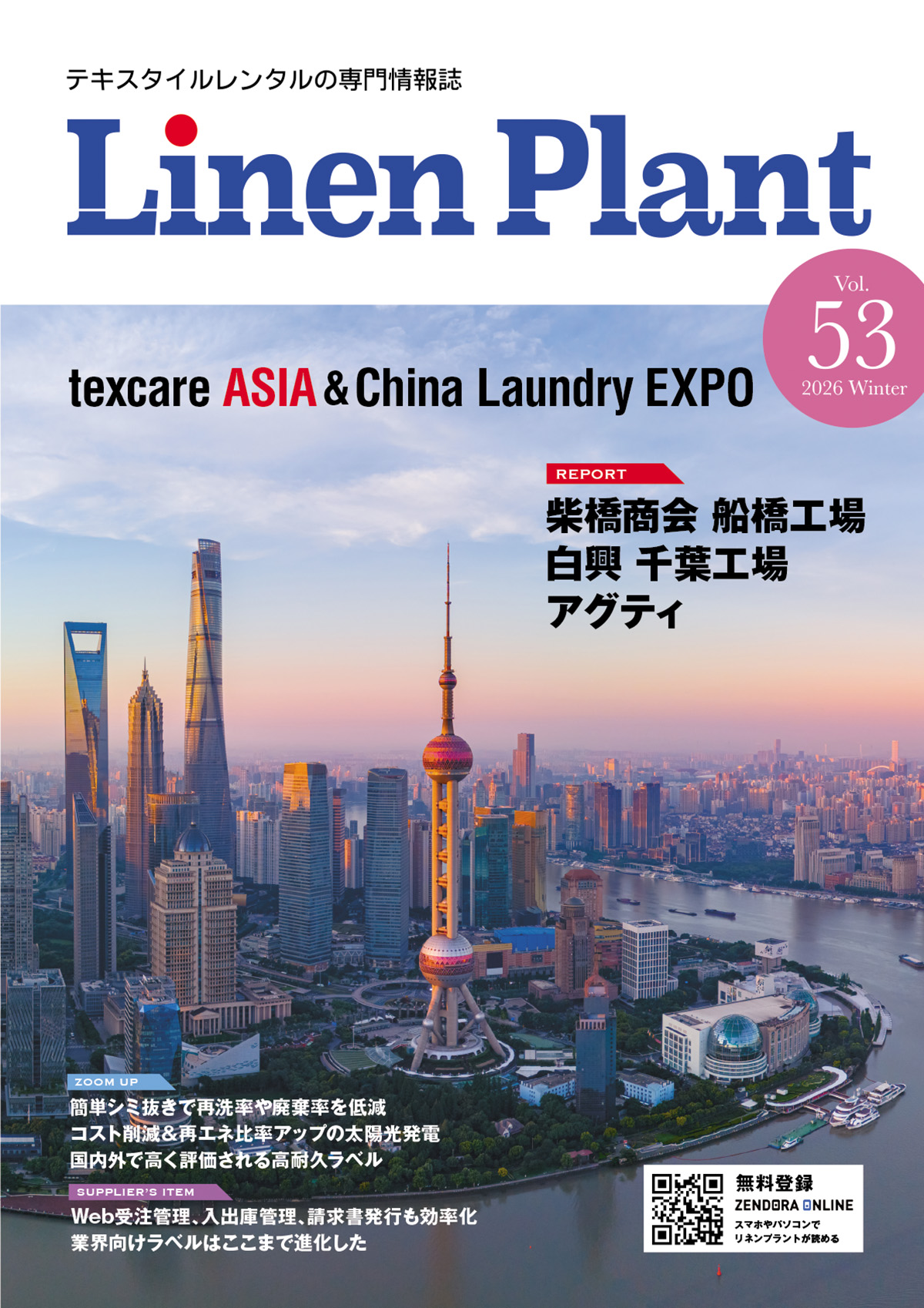- 最終更新日:
伊藤良哉の現場探訪
求められているのは何か?問題は「必要性」があるか
いつもの話になるが、日本のクリーニング業界が他の国に比べて大きなマーケットになったのは、家事代行サービス業の側面を大きく打ち出したからだった。
もともとドライクリーニングは家庭では洗濯出来ない衣類をきれいにするという加工業的なサービスを提供する業種だったが、高度経済成長期に女性の社会進出、共働き家庭増加という背景もあり、家事労働時間短縮が大きなメリットとして世の中に受入れられた。
かくしてありとあらゆるところに取次店が作られ、集中工場化が進んで短納期・低価格でサービスが提供されれば、便利さが大きな売り物となった。お金で時間を買う時代、というわけだ。
ちなみにヨーロッパのクリーニング業界がそのような形態になったのは日本より随分遅かった。今となっては意外に思われるかもしれないが、女性の社会進出はヨーロッパの方が日本より遅かった。ワイシャツのアイロンがけは主婦の仕事という習慣が長く、1990年代にようやくクリーニング店でワイシャツを扱うのが一般的になり、水洗機やワイシャツのプレス機が導入されるようになった。その裏側には、ヨーロッパにはドライクリーナーは水洗いをしない、という変な先入観というか不文律みたいな物があったのも事実だが。
さて「便利」というパワーワードで成長した日本のクリーニング業界だったが、バブル崩壊以降日本人の収入は横ばいとなり、その便利に対する対抗馬が現れた。それが「節約」。家庭洗濯できる衣料素材や家庭洗濯洗剤の開発である。「家事の時間が短縮できる」に対して、「おうちでも洗えます」がセールスとなった。
他業界でも同じことが見受けられる。かつては街のあちこちに家具屋があったが、取って代わったのがホームセンターだ。そこでは組立式家具が売り場のかなりのスペースを取っている。前回のコラムでセルフサービスについて述べたが、これもそのひとつの姿である。自分で作れば安くつく、おまけに種類が多いから自分好みや条件に合わせやすい。
そんなわけで、時間はお金で買えないと言う価値観からお金>時間という価値観にシフトした。
で、ここからなのだが、自分でやるより他者に任せた方が便利→自分でやる方が安くつく、ときて次にサービス業に求められているのは何かというと、自分では出来ないから、あるいは困ったことが起きたら他者に依頼する、という本来の役割に戻ってきているような気がしている。なんだ、当たり前の話じゃないかとなるのだが、問題は「お金には代えられないほどの必要性」がそこにあるか、ということだ。
今の世の中を見渡すとそういう商売がいろいろと増えている。害虫・害獣駆除や遺品整理なんてまさにそれだ。クリーニングに直接はあてはまらないが、そういう目で見てみると何かヒントが隠れているかもしれない。
この記事は、有料会員限定です
- 有料会員登録すると、全ての限定記事が閲覧できます。
- この記事のみ購入してお読みいただくことも可能です。
- 記事価格: 300円(税込)